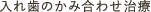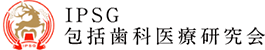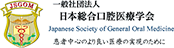HOME > 歯科について詳しく知りたい方へ > 子どもの歯ぎしりの原因は?注意点と対策方法を医師が徹底解説
歯科について詳しく知りたい方へ
子どもの歯ぎしりの原因は?注意点と対策方法を医師が徹底解説
「子どもが夜中にギリギリと歯をこすり合わせている音に驚いた」という保護者の声は少なくありません。大人と比べて小さな子どもが歯ぎしりをしていると、「何かストレスを抱えているのでは」と心配になる方も多いでしょう。
強い歯ぎしりが続いたり、噛み合わせのバランスが崩れたまま放置すると、歯のすり減りや顎・全身への影響も心配されます。
本記事では、子どもの歯ぎしりを軸に、原因や対策を年齢別に詳しく解説します。「大丈夫かな?」と迷う保護者の皆さんのご参考にしてください。
目次
子どもが歯ぎしりをする原因
 子どもの歯ぎしりには、成長過程に伴う一時的なものであったり、心理的要因や睡眠の質が関係していたりと、さまざまな背景があります。ここでは主な3つの原因について詳しく解説します。
子どもの歯ぎしりには、成長過程に伴う一時的なものであったり、心理的要因や睡眠の質が関係していたりと、さまざまな背景があります。ここでは主な3つの原因について詳しく解説します。
成長過程における歯ぎしり
まず注目したいのは「発達の一環としての歯ぎしり」です。乳歯が生え始めた赤ちゃんや、乳歯から永久歯への生え変わり期にある子どもは、上下の歯の位置やかみ合わせを無意識に確認しようとする習慣があります。
その結果、歯をこすり合わせる動作=歯ぎしりが自然に起こるのです。これは、顎や咀嚼筋の成長に伴う適応的な反応であり、多くの場合、医学的な処置を必要としません。
特に乳歯が生えそろう2~3歳頃や、6歳臼歯が生えてくる時期には、一時的に歯ぎしりが増えることがよくあります。これは、新しく生えてきた歯の感覚やかみ合わせを脳が調整しているためで起こることもあり、過度に心配する必要はありません。
また、永久歯が生えるための十分な隙間が確保されている場合は、乳歯期の歯ぎしりは問題になりにくいとされています。ただし、永久歯になってからも歯ぎしりが続く場合は、かみ合わせの確認を歯科で受けることをおすすめします。
ストレスなど心理的な歯ぎしり
子どもの歯ぎしりが長引く場合、その背景には心理的なストレスや不安が影響していることがあります。子どもは言葉で表現しにくい感情を、睡眠中の無意識な動きとして示すことがあり、その一つが歯ぎしりです。
たとえば、幼稚園や保育園での環境の変化、家庭内の緊張、親の不在や叱責などがストレスのきっかけとなることが多いです。
こうした歯ぎしりは、心身の緊張をほぐすための自己調整行動としての側面もあり、時間の経過とともに自然に落ち着く場合もあります。
一方で、歯のすり減りや顎の疲労が見られるような強い歯ぎしりの場合は、早めに小児歯科や小児科で相談し、ストレスの原因をしっかりと見極めることが重要です。適切な対応が遅れると、歯や顎に悪影響を及ぼすリスクが高まるため注意が必要です。
なお、興味深いことに、歯ぎしりはストレス発散の役割を果たしていると考えられており、歯ぎしりによってストレスが緩和されるという研究結果も報告されています。
このため、歯ぎしりそのものを過度に悪と捉えず、子どもの心身の状態を総合的に見ることが大切です。
睡眠障害などによる歯ぎしり
子どもの歯ぎしりは、睡眠の質とも深い関係があります。特に浅い眠りや中途覚醒が多い子どもでは、就寝中に歯ぎしりが現れやすくなる傾向があります。
これには、アレルギー性鼻炎や扁桃肥大などによるいびき・口呼吸、さらには不規則な生活習慣が背景にあることも少なくありません。
また、夜間の歯ぎしりは「睡眠時ブラキシズム」と呼ばれ、睡眠時無呼吸症候群といった睡眠障害の一症状として現れることもあります。
こうした場合は、歯科だけでなく耳鼻科や小児睡眠外来との連携が必要になることもあります。
年齢別に見る子どもの歯ぎしりの原因と役割
 子どもの歯ぎしりは、年齢によってその背景や意味合いが異なります。「何か問題があるのでは」と心配する保護者の声も多く聞かれますが、乳歯期の歯ぎしりは基本的に心配の必要はありません。むしろ、歯ぎしりが気になり始めるのは乳歯列が完成してからです。
子どもの歯ぎしりは、年齢によってその背景や意味合いが異なります。「何か問題があるのでは」と心配する保護者の声も多く聞かれますが、乳歯期の歯ぎしりは基本的に心配の必要はありません。むしろ、歯ぎしりが気になり始めるのは乳歯列が完成してからです。
成長の過程での自然な反応や、心身の発達と深く関わっていることが多いため、年齢に応じた理解が大切です。
ここからは、乳児期・幼児期・幼少期に分けて、それぞれの時期における歯ぎしりの原因と役割を解説します。
乳児期(0歳〜1歳)
乳児期の歯ぎしりは、生理的な発達の一部と考えられています。生後6カ月ごろから乳歯が生え始め、上下の歯が噛み合うようになると、赤ちゃんは自然と歯をこすり合わせるようになります。
これは、かみ合わせの感覚を確かめたり、口腔内の新しい刺激に順応しようとしたりする、いわば「練習」のような動きです。
また、この時期の赤ちゃんは「吸う」ことが本能的な行動であり、口腔周囲の筋肉を使うことで情緒の安定を図っています。歯ぎしりもその延長線上にあり、顎や咀嚼筋の発達を促す働きがあるとされています。
音が気になっても、歯や顎に明らかな異常が見られない限り、過度な心配は不要です。
幼児期(1歳〜3歳)
1歳から3歳の幼児期は、乳歯列が完成する重要な時期です。
また、この時期は顎の成長や歯の位置調整が活発に行われ、上下の歯のバランスを整えるために歯ぎしりが生じることも多いです。多くの場合、一過性の自然な現象として見られます。
さらに、幼児期は自我が芽生え始め、環境の変化に敏感になる時期でもあります。保育園への入園や家族環境の変化など、心理的ストレスが歯ぎしりとして現れることもあるため注意が必要です。
夜間にギリギリと音を立てる歯ぎしりが続く場合は、生活リズムや心の状態を見直す機会にしてみてください。
幼少期(3歳〜6歳)
3〜6歳の幼少期は、社会性や言語、感情表現などが急速に発達する時期です。
しかしその一方で、不安や緊張をうまく言葉にできず、無意識のうちに歯ぎしりとして表現してしまう子どももいます。たとえば、幼稚園での集団生活や友だちとの関わりに戸惑いを感じたときなどに、就寝中の歯ぎしりが見られることがあります。
この時期は、上下の歯並び(歯列アーチ)がまだ整っていないため、自然と歯が擦れ合い、乳歯のかみ合わせ部分(咬合面)が平らにすり減っていくこともあります。これは正常な成長の一環であり、多くの場合は心配いりません。
さらに、5〜6歳になると「6歳臼歯」と呼ばれる第一大臼歯が生え始め、乳歯と永久歯が混在する「混合歯列期」に入ります。この時期はかみ合わせが変化しやすく、口の中の違和感から歯ぎしりを引き起こすこともあります。
基本的には経過を見守って問題ありませんが、歯のすり減りが著しかったり、顎の痛みを訴えるような場合には、一度歯科医院で診てもらうと安心です。
子どもの歯ぎしりが酷すぎる場合の注意点と対策方法
 子どもの歯ぎしりの多くは一過性のもので、成長とともに自然におさまっていくことが多いものです。しかしながら、歯の摩耗や顎の痛み、睡眠の質の低下、さらには心理的なストレスの現れとして歯ぎしりが見られる場合には注意が必要です。
子どもの歯ぎしりの多くは一過性のもので、成長とともに自然におさまっていくことが多いものです。しかしながら、歯の摩耗や顎の痛み、睡眠の質の低下、さらには心理的なストレスの現れとして歯ぎしりが見られる場合には注意が必要です。
ここでは、歯ぎしりが特に酷いと感じられるケースでの注意点と、家庭や医療機関でできる対策について詳しく解説します。
歯の痛みや摩耗が著しい場合
歯ぎしりの影響で乳歯がすり減ってしまうことは珍しくありませんが、歯の先端が平らになっていたり、明らかな欠けやひびが見られたりする場合は注意が必要です。
歯のエナメル質が摩耗することで象牙質が露出し、冷たいものや熱いものに敏感になる知覚過敏や、痛みを訴えることもあります。
また、犬歯がうまく機能せず、奥歯が強く干渉するタイプの歯ぎしり(アンテリアガイダンスの欠如)では、咀嚼筋や顎関節、奥歯への負担が大きくなるため、特に注意が必要です。
このような場合は、歯科医院でのチェックが必須です。状態に応じて、正しい噛み合わせの治療をおすすめします。
乳歯であっても、過度な摩耗は咀嚼機能や永久歯の正常な萌出に影響する可能性もあるため、早めの対応が望まれます。
小児は痛みを訴えにくいので、痛みが出るほどの咬耗があるときは噛み合わせの重大な異常サインと捉え、矯正歯科での精査と早期介入が望まれます。
顎関節の痛みや異音がある場合
歯ぎしりは、顎の関節(顎関節)や咀嚼筋に大きな負担をかける行動です。
顎を動かすとカクカクと音がする、口を大きく開けづらい、朝起きたときに顎が痛むといった症状がある場合は、顎関節症が疑われます。
こうした症状がみられるときは、無理に口を開けさせたり様子を見るだけにせず、顎の発育を理解した専門の歯科へ受診しましょう。
治療には、、頬杖をつく、うつぶせ寝をする、硬いものをかむ習慣など、日常生活の中にある負担要因を見直すことも重要です。
症状が軽いうちに適切な対応をすることで、成長期の顎の発達に悪影響を与えるリスクを最小限に抑えることができます。
睡眠障害を併発している場合
歯ぎしりの音が非常に大きく、何度も目を覚ます、いびきをかく、朝起きても疲れているといった症状が見られる場合、単なる歯ぎしりだけでなく睡眠障害が潜んでいる可能性もあります。
特に、小児の睡眠時無呼吸症候群や、ストレス性の不眠との関連が指摘されています。睡眠の質が低下すると、成長ホルモンの分泌や脳の発達にも悪影響を及ぼすことがあるため、症状が続く場合は小児科や睡眠専門外来での評価が望まれます。
家庭では、就寝前のルーティンを整える、寝室の環境(照明、温度、音)を見直すなどの「睡眠衛生」を心がけましょう。
心理的な要因が強く、日常生活に支障がでている場合
子どもの歯ぎしりは、不安・緊張・ストレスなどの心理的要因と深く関係しています。保育園や幼稚園の人間関係、引っ越しや兄弟の誕生といった生活の変化にうまく適応できないとき、夜間に無意識のうちに歯ぎしりが強くなることがあります。
もし、日中も情緒不安定だったり、食欲不振や腹痛、登園渋りなどが見られる場合は、歯ぎしりが「心のサイン」として現れている可能性があります。
お子さんの変化に気づいたら、まずはしっかり話を聞き、安心できる環境を整えることが第一です。必要に応じて、小児心療内科や発達支援センターなどに相談することも視野に入れましょう。
子どもの歯ぎしりに対してナイトガードやマウスピースの必要性について
 子どもの歯ぎしり対策として、ナイトガード(就寝用マウスピース)の使用を検討するケースが増えています。
子どもの歯ぎしり対策として、ナイトガード(就寝用マウスピース)の使用を検討するケースが増えています。
ただし、乳歯列や混合歯列期の子どもにとっては、大人と同じように単純に装着すればよいというわけではありません。
子どもの歯ぎしりは、基本的に成長における発達の一環として起こることが多いため、大人のようにナイトガードやマウスピースをする必要はありません。
むしろ、この時期に安易にマウスピースを使用することで、顎の発達や口腔内の筋肉の発達を阻害してしまう可能性も考えられます。
ただし、ストレスなどの精神的な問題が原因で強い歯ぎしりをしているケースもあります。その場合は、自己判断せず、必ず医師や歯科医師などの専門家に相談し、マウスピースが必要かどうかを適切に判断してもらうことをおすすめします。
まとめ
子どもの歯ぎしりは、多くの場合、乳歯の発育やかみ合わせの調整、または睡眠中に見られる自然な生理的反応として起こります。永久歯が生えるための十分な隙間があれば、乳歯期の歯ぎしりは基本的に問題ありません。
ただし、永久歯に生え変わったあとも歯ぎしりが続く場合は、一度かみ合わせの状態を確認してもらうことをおすすめします。
また、歯が著しくすり減っていたり、顎に痛みを感じたり、睡眠の質が悪くなるような場合は、早めに専門機関を受診して適切なケアを受けることが大切です。
さらに、心身の緊張が強い子どもでは、歯ぎしりがストレスのはけ口となっていることもあります。この場合、アンテリアガイダンスがうまく機能していないと、奥歯や顎関節に過度な負担がかかり、肩こりや頭痛など全身症状につながることもあるため注意が必要です。
歯ぎしりの音や見た目だけで過度に心配せず、子どもの年齢や発達段階、生活環境、心理的な状態などを総合的に考慮しながら、必要に応じて専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
この記事を書いた人
◆経歴
2000年 明海大学歯学部 卒業
2000年~2006年 明海大学病院歯周病科 勤務
2012年9月 あらやしき歯科医院 開業
◆所属・資格
IPSG包括歯科医療研究会 副会長
明海大学歯周病学分野同門会
日本総合口腔医療学会 口腔総合医認定医 常任理事
オーラルビューティーフード協会 理事
日本医歯薬専門学校非常勤講師
日本顎咬合学会 かみ合わせ認定医
2025年10月20日 16:59